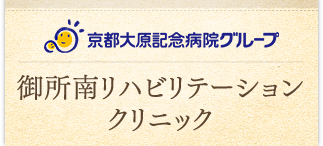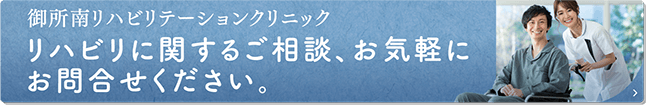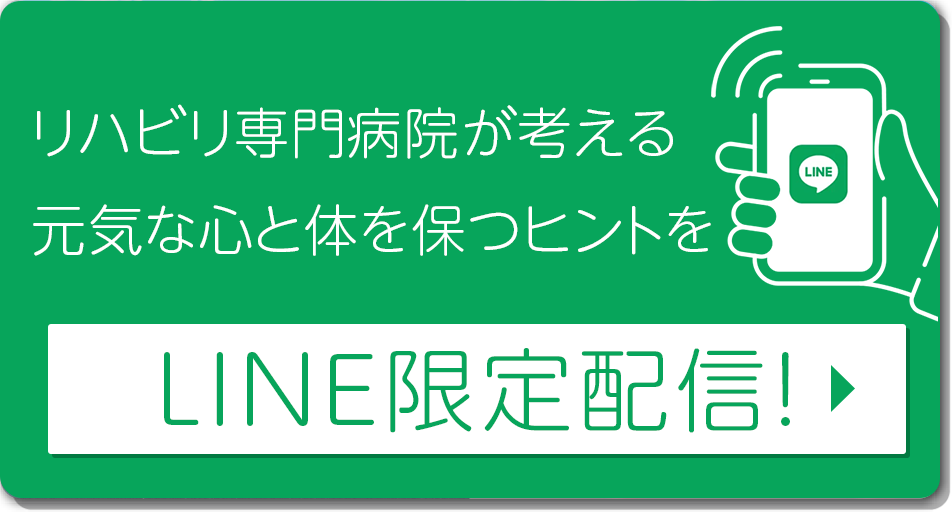パーキンソン病のリハビリテーション方法を知りたい!原因や症状もご紹介
こんにちは、御所南リハビリテーションクリニックです!
「手足が震える」「動きが遅くなる」などの症状が起こると「パーキンソン病」の可能性があります。
高齢者に多い病気ですが、若者も発症することがあります。
現在の医療ではパーキンソン病の完治は難しいですが、リハビリテーションや正しい治療によって、進行を緩やかにすることが可能です。
病気と上手く付き合っていく為の、パーキンソン病の症状や原因、治療やリハビリテーションについてご紹介します。
■自宅でできる 「 パーキンソン病のストレッチ体操 」 動画を公開中!
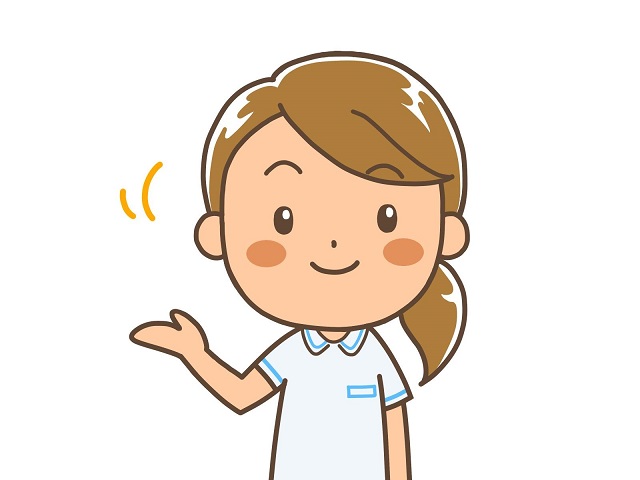
「パーキンソン病」とは?原因と症状を知っておこう
イギリスのジェームズ・パーキンソン医師が報告したという「パーキンソン病」。
パーキンソン病は、脳の中の神経に異常が起こることで発病し、50歳~60歳以降に多くみられます(40歳以下で発症するものは若年性パーキンソン病と呼ばれます)。
ゆっくりと進行する病気で、日本では約10万人以上(約1,000人に1人)が発病していると推定されています。
パーキンソン病の原因
パーキンソン病は、脳の奥の「黒質」と呼ばれる場所にあるドパミン神経が減少することになって発症します。
ドパミンとは、人間が思った通りに体が動くよう運動の調節を司令している「神経伝達物質」のことをいいます。
パーキンソン病になると正常のドパミン量の20%程度に減少し、脳内での運動調節が出来なくなり、体の動きに障害が現れます。
その他にも非運動症状と言って、中枢のアセチルコリンやセロトニンなども減少するためにうつ症状・睡眠障害などの精神的症状が現れたり、自律神経もダメージを受けるので、便秘・頻尿・起立性低血圧が現れることもあります。
近年、パーキンソン病の診断は「SPECT(スペクト)検査方法」で、行われます。
この検査で脳内のドパミン神経の状態を見ることが出来ます。
画像撮影装置のベッドに仰向けになった状態で、頭部を撮影します。
パーキンソン病で起こる代表的な4つの症状
パーキンソン病の代表的な症状は、「振戦(しんせん)」「動作緩慢(かんまん)」「筋固縮(きんこしゅく)」「姿勢反射障害」と4つあります。
病気が進行すると日常生活に支障をきたします。
振戦(しんせん)
安静にしているときに、手や足に細かな震えが生じます。
動作緩慢(かんまん)
「無動」や「寡動」と表現することもあります。
動作が鈍くなり、歩く速度が遅くなります。
歩幅も狭くなり、腕の振りも小さくなるのが特徴です。
筋固縮(きんこしゅく)
腕や足、体幹の筋肉が強ばって固くなりスムーズに動かすことが困難になります。
関節の曲げ伸ばしをした際カクカクした不自然な動き方(歯車現象)をします。
姿勢反射障害
体のバランスが悪くなり、転びやすくなります。
重心が傾いてしまうと元の姿勢に戻すことが難しくなります。
※姿勢反射障害は発症早期からでは無く、数年経過してから起こる事が多いと言われています。
パーキンソン病のリハビリテーションにはどんな方法がある?

パーキンソン病は進行すると運動機能が低下します。
今自分でできることを今後もできるように、リハビリテーションを行うことが大切です。
今回はパーキンソン病に必要な体操と「LSVTⓇ LOUD&BIG」をご紹介します。
1.体力の低下を防ぎ筋肉や関節を柔らかくする体操
障害が起きている場所を中心に、全身の動きがスムーズになるよう、また可動域が少しでも広がり、筋固縮が進まないように様々なストレッチを組み合わせて行います。
以下は、パーキンソン体操の例です。
顔の運動
口を大きく開けて閉じてを繰り返し、口を閉じたまま頬を膨らませたり、顔をしかめたりゆるめたりします。
顔の筋肉のこわばりやしゃべりにくさを改善します。
頭と首の運動
頭を左右にゆっくり倒したり回したりします。
痛みが出ない程度に動かし、頭と首の筋肉をストレッチします。
肩や腕、手や指の運動
両手を合わせ、腕を頭の上に向けてゆっくり上げる、手を背中の後ろで握り上げ下げするなど関節の柔軟性を高め動きやすくします。
また、手指がスムーズに動くように手首回しや指回しも組み合わせます。
座って行う運動
1)椅子にしっかり座り、両手を頭の後ろに組み、体をゆっくり前に倒した後戻す(前屈)。
2)慣れてきたら座った状態から体をゆっくり左右にひねる。
3)座ったまま太ももの上げ下げや、膝の曲げ伸ばしをしてもよいでしょう。
体を左右にひねる場合は、椅子の背もたれに手をかけても良いですが、腕の力で体を引っ張るのではなく、あくまで体を支えるために両手で手をかけることが大切です。
上半身だけでも筋肉を伸ばすことで、全身の血行が良くなります。
立って行う運動
1)腰と足の筋肉を柔らかくするため、立ったまま体をゆっくり前に曲げる。
2)立ったまま体を左右にゆっくりねじり、横側の筋肉を柔らかくする。
3)壁に向かって両手をつき、胸をつけるように背筋を伸ばす。可能であれば壁に向かって緩く腕立てを行う。
いずれも両足は肩幅に開き、ゆっくりと呼吸をしながら動かすことで筋肉を伸ばし全身の循環を良くします。
2. アメリカで考案された「 LSVTⓇ LOUD&BIG 」
LSVTⓇはパーキンソン病患者さんの声を大きくする・動きを大きくする効果が期待できます。
LSVTⓇの認定を受けた療法士(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)のみが、施行を認められます。
LSVTⓇ LOUDでは、発話明瞭度の改善を目的に意識的に大きな声を出すトレーニングを行います。
大きく声を出す習慣をつけることで、日常会話がスムーズに行えるようになります。
LSVT BIGは、大きく体を動かすことを意識するトレーニングです。
集中して大きな動きを繰り返し、正常に近い動きの獲得を目指します。
LSVTⓇ LOUD&BIGは、訓練で習得した動作を自宅でも出来るように指導していくことも目的の一つです。
訓練が終わればそこでリハビリテーションも終了。ではなく、続ける事で初めて効果が持続します。
習得した動作を反復することが大切です。
パーキンソン病は正しい治療とリハビリテーションが大切!
パーキンソン病は、正しい治療とリハビリテーションにより進行を緩やかにすることが可能です。
また、手足が震える、歩きにくくなったなど体に違和感があったら早めに受診することが大切です。
パーキンソン病の治療の基本は薬物治療です。主には減少しているドパミンを補充して症状を軽くする方法が行われます。
病状の進行状況を常に把握しながら投薬(ドパミンの原料となるレボドパ(L-ドパ)製剤とドパミンの代わりをするドーパミン受容体作動薬(ドパミンアゴニスト)など)を行い、並行してリハビリテーションを行うことで、症状の進行を最小限に抑えられます。
病気を完治することは難しいですが、正しい投薬治療やリハビリテーションによって歩行障害や生活動作の障害を緩和することができます。
大切な家族と健全な生活を送るためにも、しっかりと症状を把握し様々な治療方法を組み合わせながら、無理のないリハビリテーションを行いましょう。
しっかり症状を把握し様々な治療方法を組み合わせながら、パーキンソン病と上手に付き合いましょう。
関連記事
- 2019年11月05日
- 「作業療法士」の役割は?リハビリテーションにおける仕事内容
- 2020年04月10日
- 脳卒中のリハビリは「急性期から始める」ことが大切!
- 2018年01月23日
- 嚥下障害のリハビリにはどんなものがあるの?
- 2016年10月17日
- リハビリテーションを頑張るあなたの糧に!おススメ映画のご紹介
- 2020年04月13日
- 寝たきりでも筋力低下を予防しよう!リハビリのポイントをご紹介
- 2017年12月12日
- 遂行機能障害とは?計画的な行動が出来ない症状について