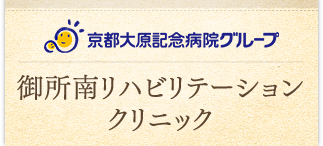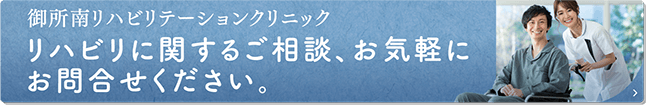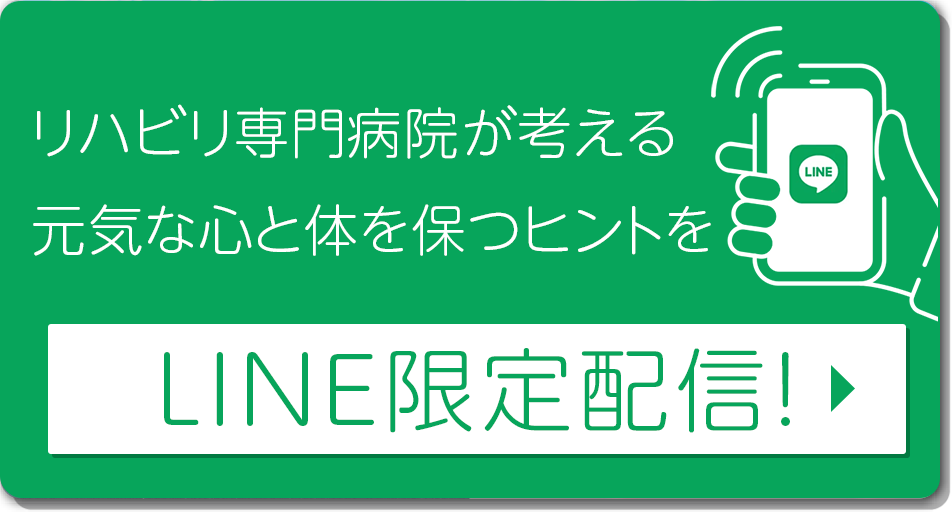骨折後のリハビリテーションはいつから?早く元の生活を送るには
こんにちは、御所南リハビリテーションクリニックです!
「骨折後のリハビリ」の現状が変わってきていること、ご存知でしたか?
今回はそんな「骨折後のリハビリ」についてご紹介します。
以前は、「ギブスが取れてからリハビリ」を開始するのが一般的でした。
それは、クリニックにリハビリテーション専門施設を併設していなかったり、併設していても十分なリハビリ専門職スタッフが足りていなかったことが上げられます。
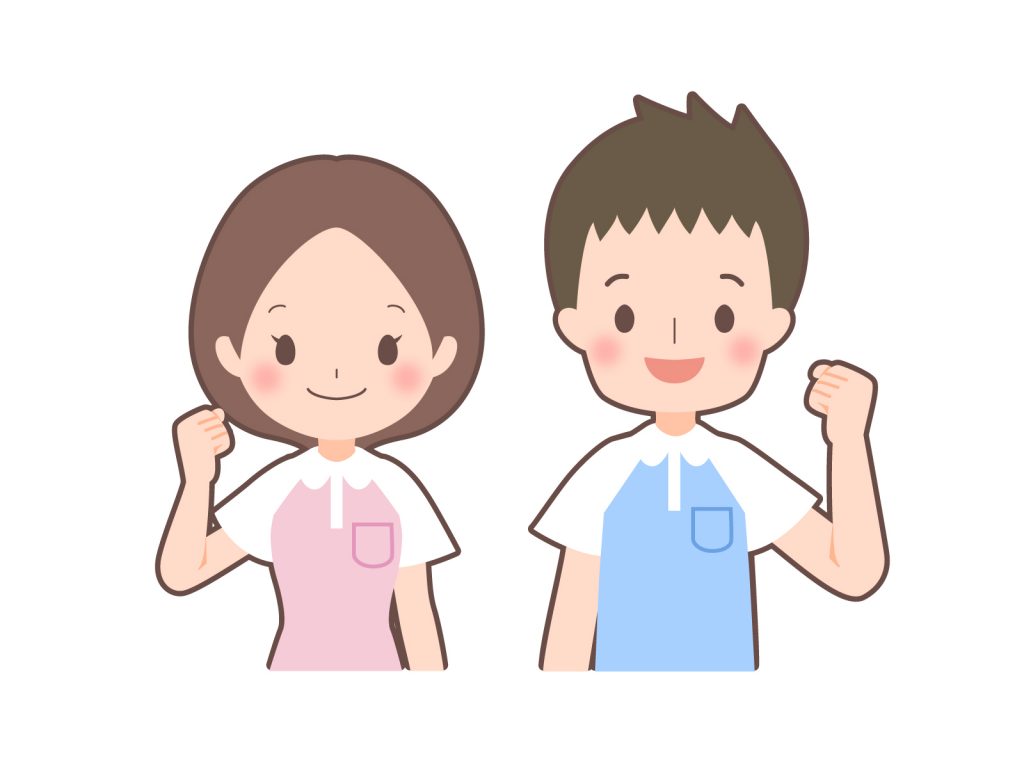
骨折後のリハビリは「負傷後数日」もしくは「処置をした後」から
負傷後数日~数週間を「急性期」と呼びます。
治癒にかかる期間は負傷時の年齢や本来の体力、負傷部位や手術の有無にも左右されますが、一般的に負傷前の状態に戻るまでおおむね3か月~6か月かかると考えられています。
負傷部位の癒合(骨と骨が付着する)日数の目安として、
中手骨:2週 肋骨:3週 鎖骨:4週 上腕骨:5週 上腕骨幹部:6週 脛骨:7週 上腕骨頸部:7週 下腿骨:8週 大腿骨幹部:8週 大腿骨頸部:12週
骨折の治癒過程の目安として、
・負傷後10日前後:負傷部位の周りの血液から血腫を作り、出血が止まると炎症が起こる時期
・負傷後10~20日頃:柔らかな組織が、繊維状→軟骨程度に再生
・負傷後20~60日頃:軟骨→一般的な骨状に変化するが、硬度には個人差アリ
・負傷後90~180日頃:元の骨組織にほぼ近い状態まで回復
(同程度の損傷であれば上半身の骨折より下半身の骨折の方が時間はかかりやすくなります。)
もちろん負傷直後は痛みも強い上に、骨折部位の周辺は炎症や筋肉の破損を伴っていることが多く、まずは負傷部位(骨折部)を安静に、骨転位があれば正しい部位へ安定させることが最重要となります。
ただし、筋肉や関節は数日動かさなかっただけでも萎縮(いしゅく:筋繊維がやせ細った状態)や拘縮(こうしゅく:関節がこりかたまって動きが悪くなる状態)が始まりますので、痛みを伴わない部位のリハビリは骨折の処置をした後から始めることが理想となります。
負傷部位につながる筋力、関節の可動域の安定がリハビリのコツ
骨折の処置をした後から、負傷部位の周りから動かし始めます。
例えば手腕のケガでは「手首の関節近くにある」「橈骨(とうこつ)」と「尺骨(しゃっこつ)」の骨折が多いのですが、これらの部位を損傷していても指先や上腕の骨、筋肉には問題がない場合、負傷後数日のリハビリは「手の指」「ヒジ」「肩」を動かすことから訓練を始めます。
一見関係がないように思えるかもしれません。
しかし、いざ骨がつながり始め、本格的なリハビリを開始したとき、負傷部位につながる筋力や可動域が落ちてしまうという合併症を起こす場合があります。
連動する部位の調整も必要となり、結果的にリハビリに要する期間が長くなります。
そういった症状を予防するためにも、先の例でいえば「指を曲げ伸ばしてみる」「肩をゆっくり回す」といった運動を負傷後数日から始めるのが効果的です。
骨折後のリハビリは無理ない程度に動く部位を増やす
いざ骨がつながり始め、本格的なリハビリが開始したとき、しっかり急性期リハビリテーションを始めていたにもかかわらず自分の筋力が落ちていることに驚いた、という声をよく耳にします。
しかし、焦らず医師や理学療法士・作業療法士と連携しながらリハビリテーションを続けることが大切です。
この時期は「負傷部位の筋トレ」や「実際の日常動作などの練習」が中心となりますが、単にメニューをこなすのではなくゲーム感覚でリハビリの項目を徐々に増やしたり、できることを少しずつ確実に増やすと効率よくリハビリを実施できます。
ここで気を付けたいのが「自己判断でリハビリ計画を変更しない」ことです。
スポーツでけがをしてしまった学生さんや、仕事に一日でも早く復職や復帰したいと考える社会人の患者さんが無理をしてしまい、再骨折してしまうケースも珍しくありません。
特に下半身のリハビリは、骨の結合度合いを確認しながら自身の体重を少しずつかけて骨に適度な刺激を入れもとに戻す「荷重制限」は上半身以上に重要となります。
多少の痛みや違和感は、リハビリ中は避けて通れませんが、痛み止めを常用したくなるような痛みを感じた場合は負荷のかけすぎですので、必ず医師や理学療法士に相談しましょう。
骨折後は早めにリハビリを。負傷部位の周りから無理なく!

ケガの中でも本人の心身のダメージが多い「骨折」ですが、しっかりリハビリを行うことで元の健康な生活や歩行に近づけることが可能になります。
以前は「ギブスが取れてからリハビリ」を開始するのが一般的でしたが、現在は「負傷後数日」もしくは「処置をした後」からが最適とされています。
負傷部位の腫れが引き、痛みを感じにくくなったら、負傷部位の周りから始めていきましょう。
「指を曲げ伸ばしてみる」「肩をゆっくり回す」といった簡単な運動から進めると良いですね。
何より、焦らず医師や理学療法士・作業療法士と連携しながらリハビリテーションを行うことが大切です。
痛み止めを常用したくなるような痛み(激痛)を感じた場合は負荷のかけすぎですので、医師や理学療法士に相談し、焦らず確実に一歩ずつリハビリを進めていきましょうね。
関連記事
- 2020年04月06日
- 歩行のリハビリ方法について知ろう!歩行訓練の種類やポイント
- 2016年10月17日
- リハビリテーションを頑張るあなたの糧に!おススメ映画のご紹介
- 2020年04月17日
- 膝のリハビリ方法とは?自分でできる変形性膝関節症の対処法も紹介
- 2019年09月09日
- 高齢者のリハビリにおける注意点は?体力の想定、回復状態の把握が大切
- 2020年04月13日
- 寝たきりでも筋力低下を予防しよう!リハビリのポイントをご紹介
- 2019年09月23日
- リハビリテーションで活躍する資格にはどんな種類があるの?